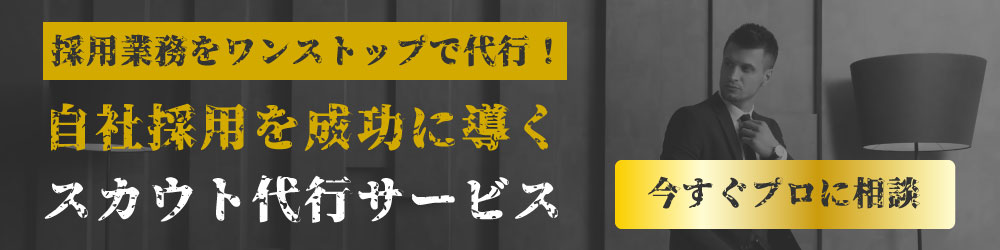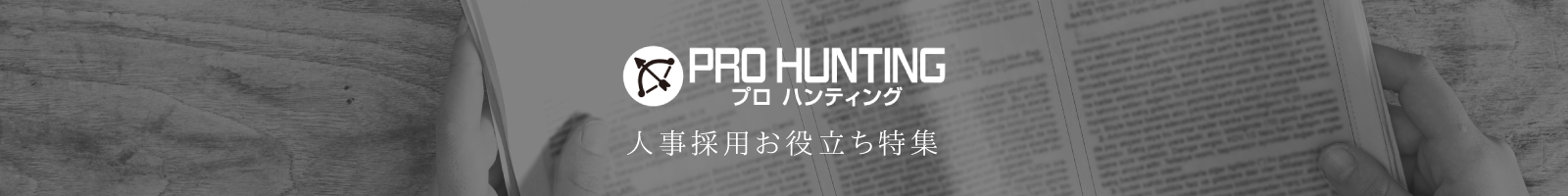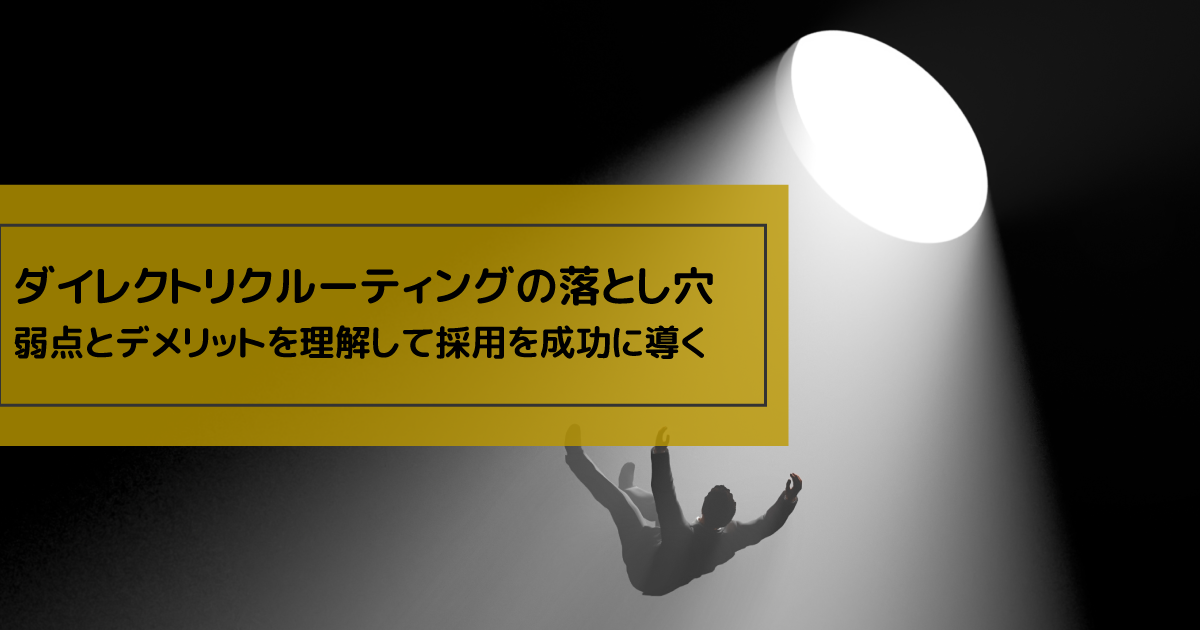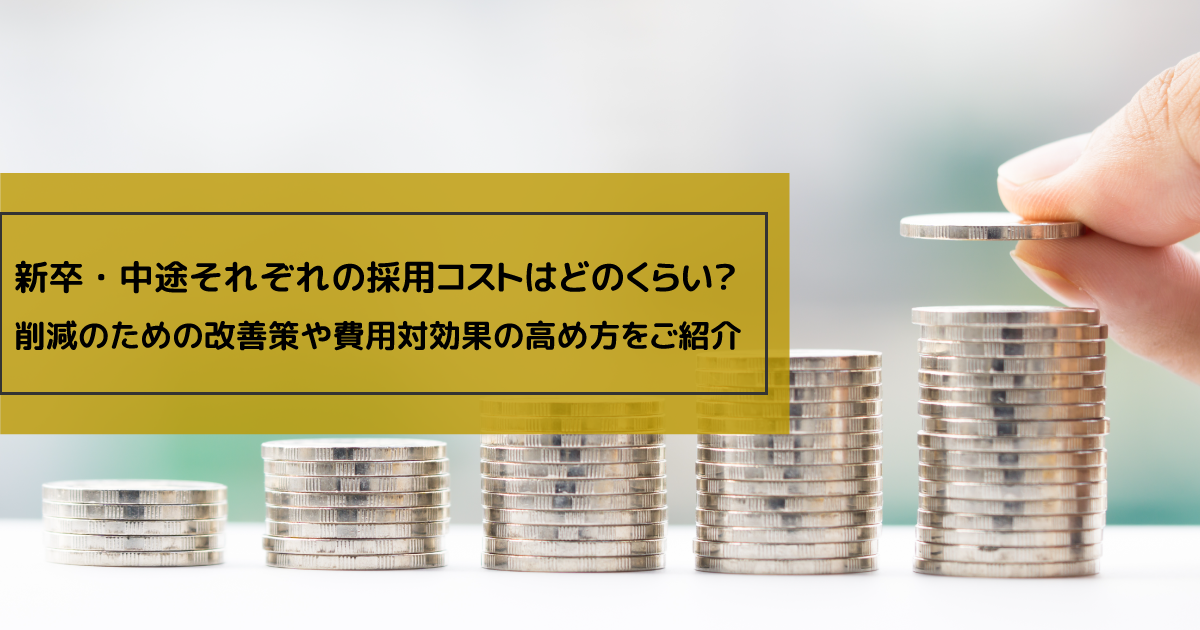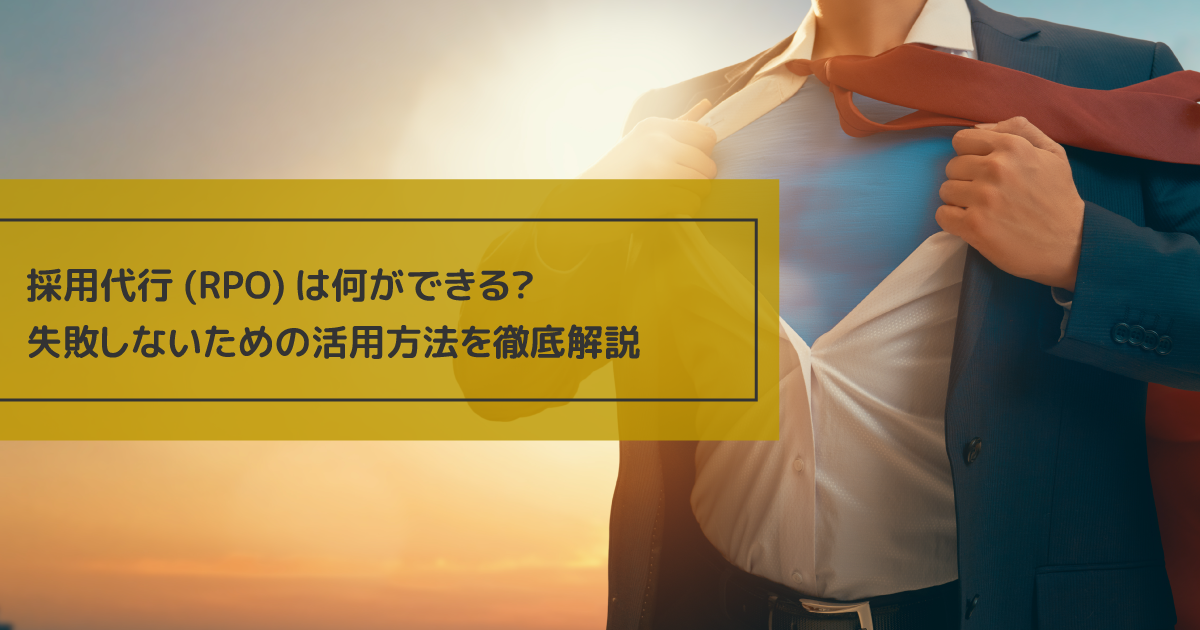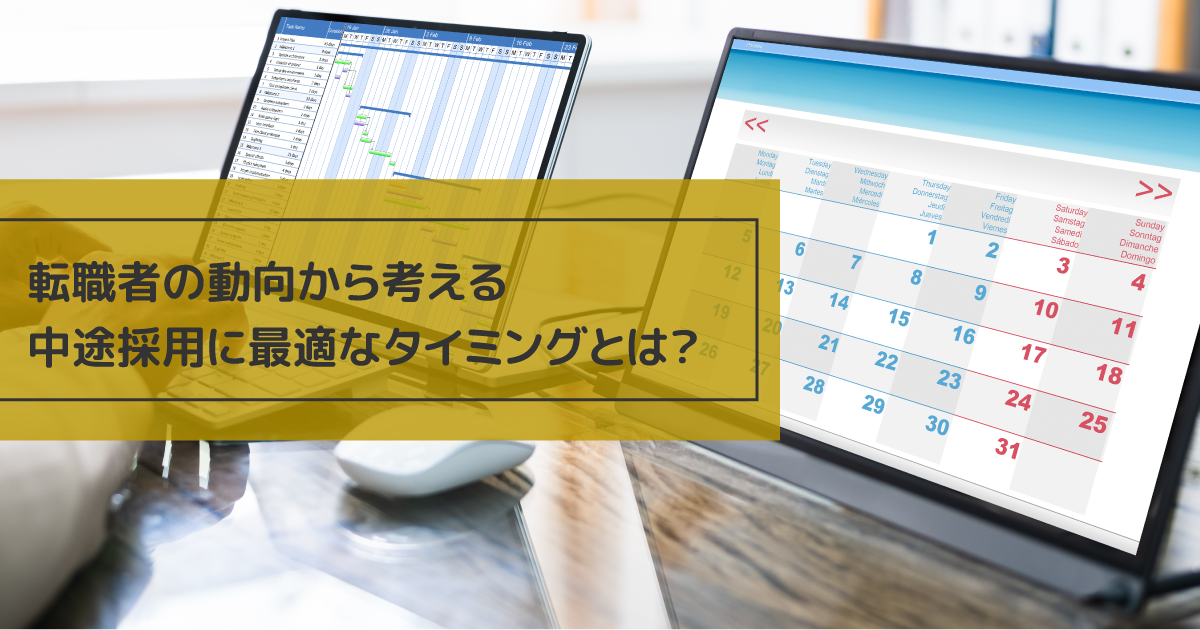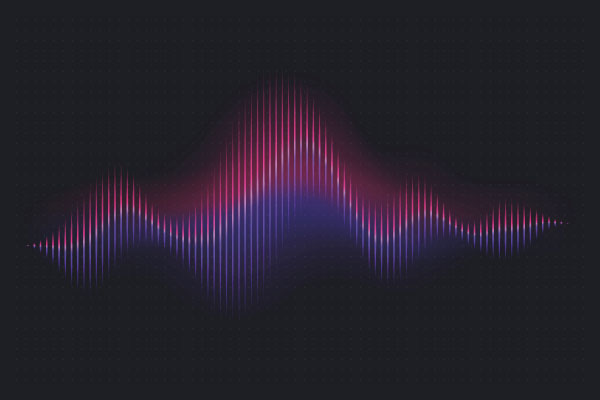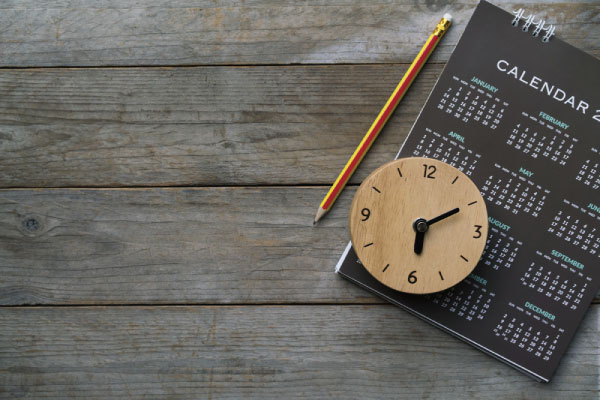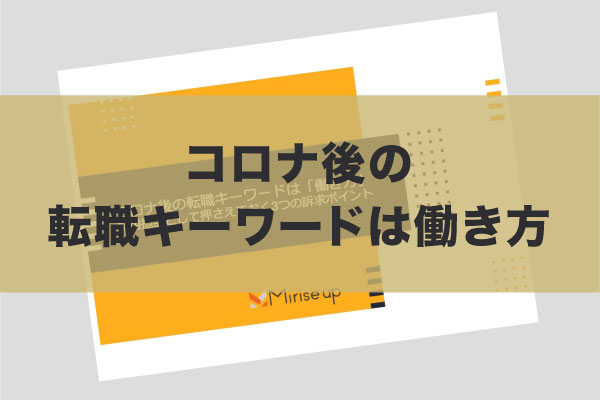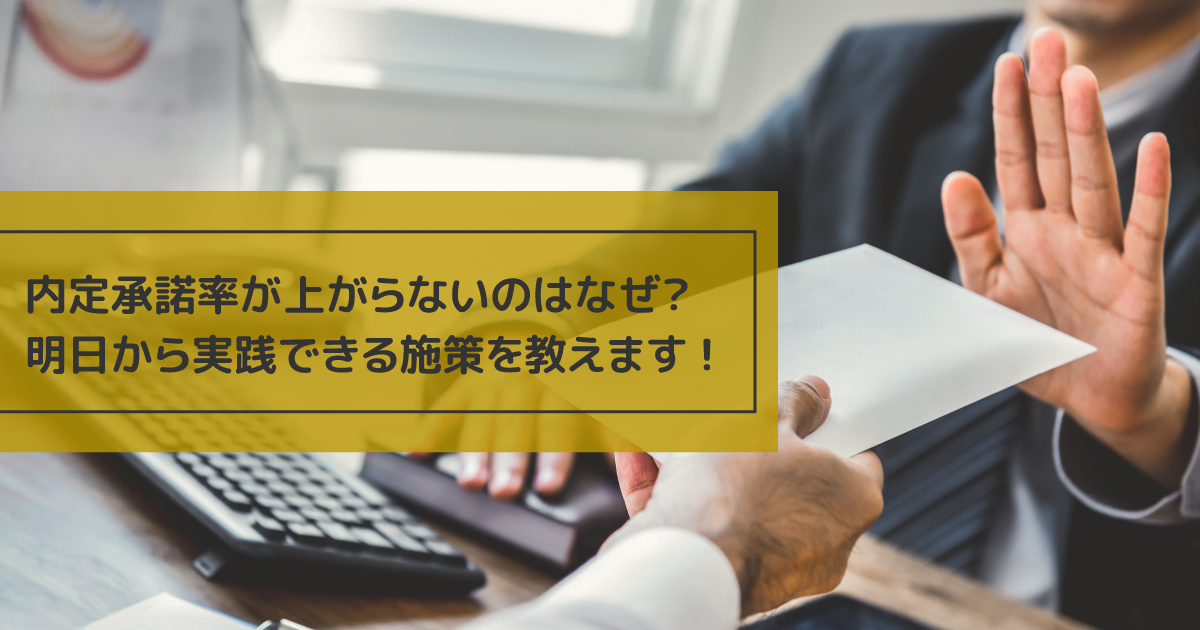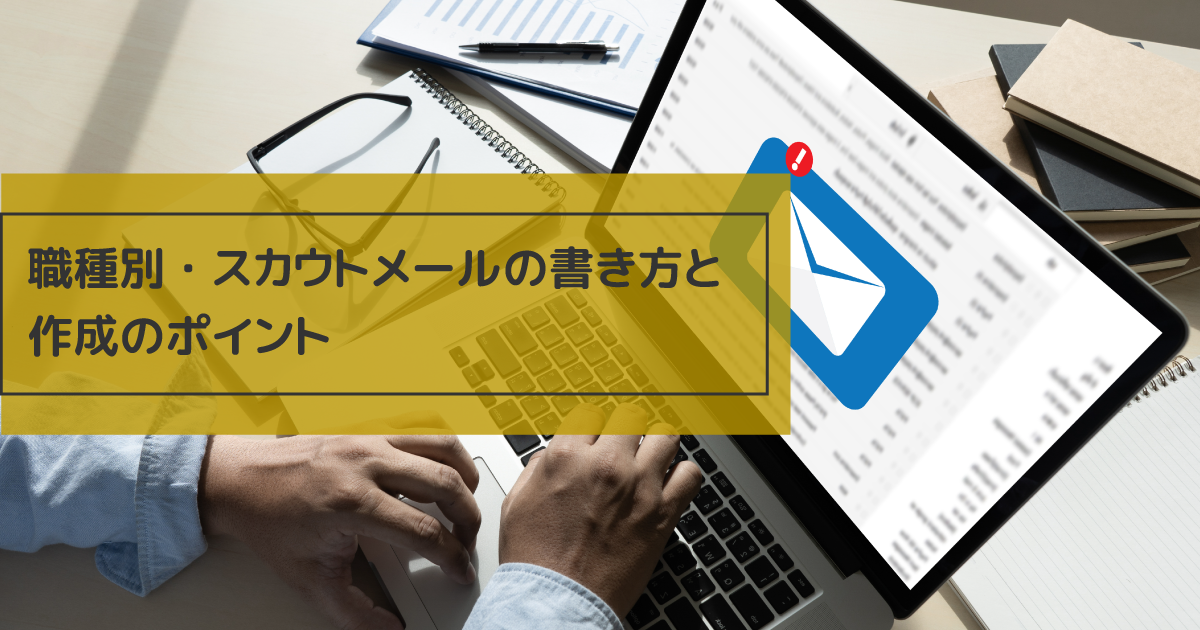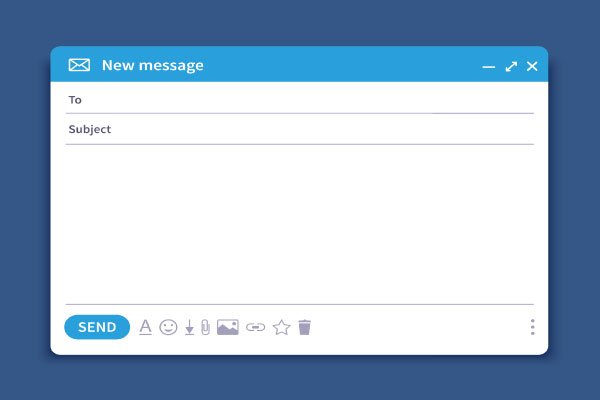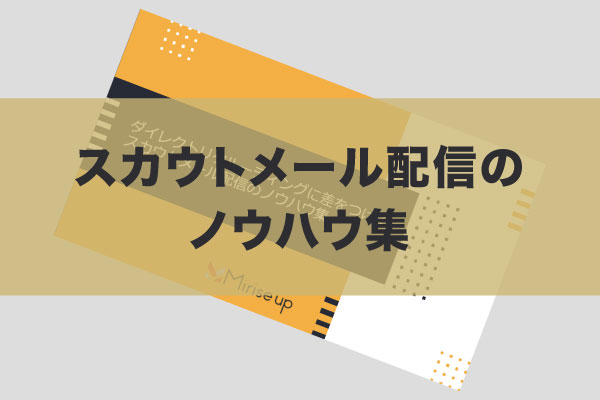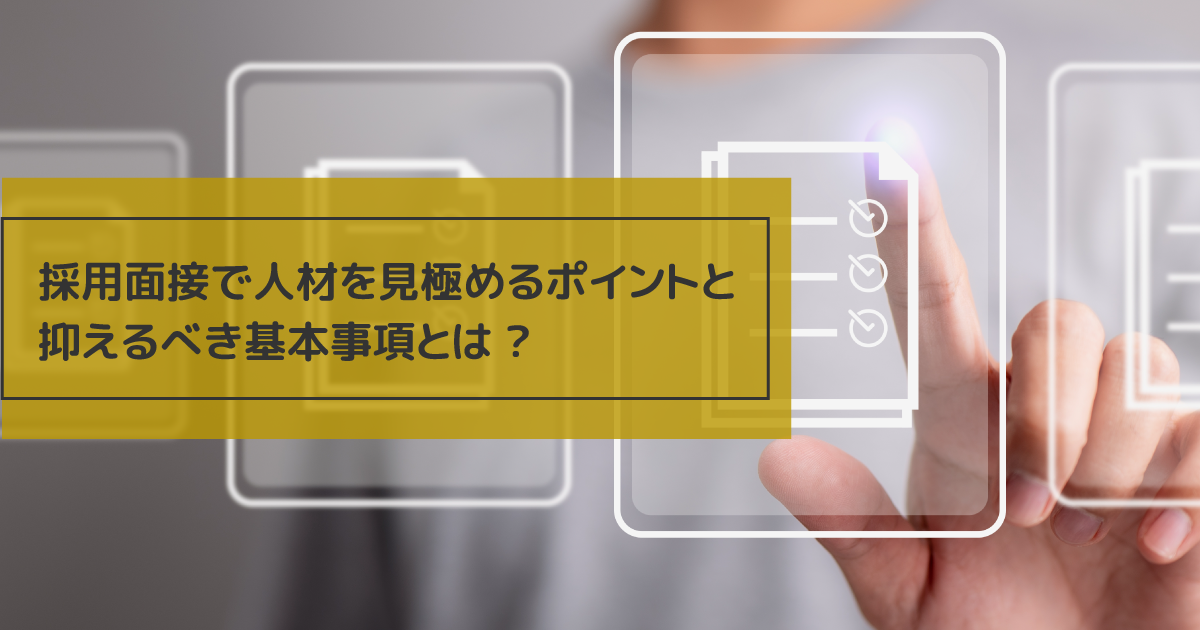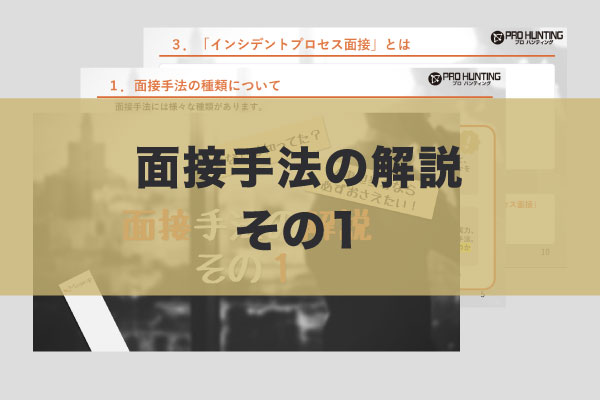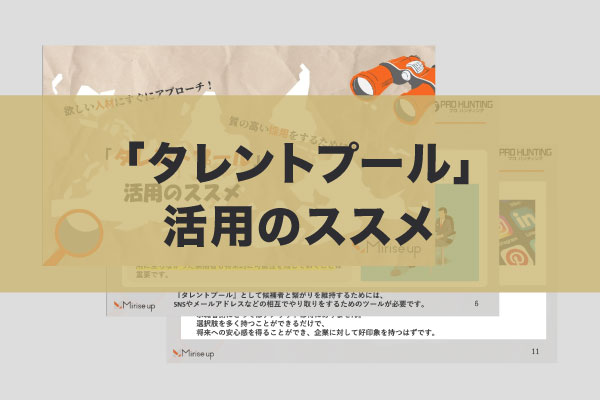働き方改革やコロナ禍で労働者を取り巻く環境は大きく変わり、併せて、採用市場も大きく変化しています。
少子高齢化から労働力不足が懸念され、企業は優秀な人材を獲得するために、求職者を“待つ”方法から、自ら“獲得”しに行く動きを見せています。
ダイレクトリクルーディングは、企業から求職者へ働きかける方法で、売り手市場の中で、メリットの多い方法ですが、運用していくにあたり、弱点やデメリットもあります。
今回はダイレクトリクルーティングを運用行く上で、理解すべき点や成功に導くポイントについてご紹介していきます。
ダイレクトリクルーディングのデメリット

ダイレクトリクルーティングにはメリットもありますが、次の2点のデメリットがあります。その点を踏まえた上で導入する必要があります。
- 社員の業務負担が増える
- 採用までに時間が掛かる
では、2点のデメリットについて詳しく見ていきましょう。
・社員の業務負担が増える
ダイレクトリクルーティングは企業が採用したいと感じる求職者をスカウトして採用へ導く方法です。
スカウトする方法はメールが基本ですが、候補者の選定、メール文書のテンプレートの作成、返信が来た応募者へ次の対応など、多くの作業工程があります。
候補者の選定1つ取ってみても候補者を選ぶ基準の設定、職種別など候補者ごとのテンプレートの作成、応募者から来たメールに、面接や交流会への参加など、反応の有った候補者ごとに、細かな対応をしなければなりません。
またスカウトメールを送っても返信があるのは約3割と言われており、希望するスキルや人物を必要数採用するには、採用者の何倍もの人へスカウトメールを送る必要があります。
1回目では関心を持って貰えなくても、タイミング次第では興味を持って貰える可能性もあるので、同じ人へ何度も定期的にスカウトメールを送るなど、社員の業務負担は多い方法です。
・採用に時間が掛かる
採用活動が必要になるのは退職者の補充、事業拡大のためなど、さまざまな理由があります。
ダイレクトリクルーティングは、急な退職者の発生など、急いで人を採用したい場合には向いていません。
理由はダイレクトリクルーティングは中長期向きの採用方法だからです。
ダイレクトリクルーティングは企業が求める人材へスカウトし、業務内容や理念など、企業に興味を持って貰うことからスタートします。
一般的な採用方法のように求職者の方が、企業理念や業務内容を理解したうえで、応募してくる方法とは対照的です。
入社して欲しい人物に定期的な連絡や交流会の開催などで、自社を理解してもらうことから始めるので、採用まで時間を要します。
このようにダイレクトリクルーティングはスタート時点が、求職者の方から応募してくる方法とは異なり、採用までに時間が掛かるという事を覚えておきましょう。
ダイレクトリクルーティングが注目される背景

売り手市場に加え、働き方が多様化すると働き手はより条件の良い職場を求めるようになり、人の動きも流動的になります。
そこで企業は優秀な人材を獲得するための対策として、高額な費用を掛けて転職サイトを利用したり、求人広告を頻繁に出したりして、人材を採用するため、各社競争が激しさを増していきます。
ただし採用活動に掛ける費用も労力にも限りがある中小企業では、高額なサイトや求人広告に費用を掛ける事や、採用活動に労力を掛けることは出来ません。
そこで、効率的な採用活動を行うため、次の2点が重視されるようになりました。
- 費用負担の軽減
- 直接的な方法で採用活動期間の短縮
上記2点の方法として無料で利用できるSNSを使った求人募集や、社員が知人や友人を紹介するリファラル採用などが行われるようになり、転職サイトよりリーズナブルに利用できる、ダイレクトリクルーティングに注目を集める企業が増えてきたのです。
ダイレクトリクルーティングの流れ

ダイレクトリクルーティングの流れは、次のようになります。
| ①スカウト候補者の選考 ②スカウト文書テンプレートの作成 ③スカウト文書送付 ④返信が来た候補者に返事を出す ⑤選考を絞る ⑥合否の連絡をする |
① スカウト候補者の選考
たくさんの転職希望者の中から、自社の求めるスキルや経験を持つ人材を絞ります。
スカウトの候補者は交流会やイベントなどに参加した方、SNSで繋がりのある方、ダイレクトリクルーティングサービスに登録している方、などが挙げられるでしょう。
② スカウト文書テンプレートの作成
スカウト候補者が絞られたら、送付する文書のテンプレートを作成しておきます。
職種別や繋がりのあった方法ごとに、準備しておくと良いでしょう。
③ スカウト文書送付
作成したスカウト文書を候補者に送付します。送付は、テンプレートを元に、ありきたりな文章ではなく、スカウトする人物一人一人にあった文章を送付します。
送付する時間帯は、会社の業務時間内に行うようにしましょう。
④ 返信が来た候補者に返事を出す
スカウトメールに返信が来た候補者にはすみやかに返事を出すようにします。
返信が来たという事は、少なくとも御社に興味があり、ビジネスマナーのしっかりしている人だと判断できます。
期待した返事でなくても、返信の有った候補者には、今後ビジネス上何らかのつながりができるかもしれませんので、返事を出すようにしましょう。
ダイレクトリクルーティングのメリット
ダイレクトリクルーティングのメリットについて、見てきます。
・転職潜在層にもアプローチできる
優秀な人材は水面下にいることも多く、なかなか転職層の表面に上がって来る事はありません。
すぐに転職は考えていないが機会があればより条件の合う職場に転職したいと考えている、いわゆる転職潜在層にもアプローチできるのがダイレクトリクルーティングです。
SNSや交流会などで過去に繋がりがあった方などにスカウトメールを送り、まずは自社に興味を持ってもらうことからスタートします。
何度かSNSで連絡を取り合ったり、イベントなどに誘ったりすることで、お互いを理解を深め、採用へと繋げていきます。
・求める人材に的を絞り探すことが出来る
ダイレクトリクルーティングは繋がりのあった人物の中から、求める人材に向け企業側が的を絞って、アプローチが出来ます。
SNSのプロフィールや過去の動向から人物像やスキルなどを知ることが出来るので、そこから的を絞ることが出来ます。
・採用活動のコスト低減につながる
求人サイトを利用すると、高額な費用になることがあります。
思った人材が集まらなければ、何度も掲載する必要があり費用負担が大きくなります。
また求人広告では求人広告を見た求職者にしか、情報が届かず、狙った母集団が形成されにくいデメリットがあります。
ダイレクトリクルーティングはSNSなどのつながりであれば無料でスカウト可能ですし、ダイレクトリクルーティングサイトを利用しても、求人サイトよりリーズナブルな価格で利用する事が可能で採用コストを抑えることが出来ます。
ダイレクトリクルーティングを成功へ繋げるポイント

ダイレクトリクルーティングを成功繋げるには、いくつかのポイントがあります。
ダイレクトリクルーティングは企業側からこの会社に入りたいと感じてもらう必要がありますから、企業自身に魅力が無ければなりません。
自社自身の魅力を高め、情報発信を行い、採用活動を自社自身で構築していくことが、成功への近道となります。
・魅力的な会社作り
まずはスカウトする相手に自社の事を知ってもらい、ぜひ入社したいと思われるような会社作りが必要です。
どの採用方法でも同様ですが、この企業に入社すると待遇面で満足できる、仕事と家庭の両立が上手くいく、自分が成長できるなど、従業員が満足した社会生活を送ることが出来る企業作りを行って行く必要があります。
・企業情報発信に力を入れる
どんなに魅力ある会社でも情報が発信されていなければ、求職者に届きません。
SNSを始め、自社HPなど費用を掛けてなくても、企業情報を発信する方法はたくさんあります。
どのような事業を行っているのか、事業規模や今後の事業展開など、積極的に発信していきましょう。
情報は正確なものを出来るだけ早く定期的に発信するようにすると、閲覧者に興味を持って貰いやすくなります。
・採用作業の仕組みを作る
人が不足したら募集をし、採用したら採用活動は終了ではありません。
今回の応募状況はどうだったのか、希望に近い母集団が形成できたのか、応募から採用までの流れはスムーズだったか、というように振り返りましょう。
もう一つ、大切なのが採用後の採用者の動きです。
働く環境に問題は生じてないか、求める成果を出せているかというように、採用後の動きについても、フィードバックを行い、採用作業の仕組みを作っていきましょう。
・スカウトメールを工夫しよう
ダイレクトリクルーティングで大切なのがスカウトメールの内容です。
スカウトメールを送ってもほとんど反応が無い場合、メールの内容を一度振り返ってみる必要があります。
・申し込んだ相手の魅力を盛り込もう
ネット上でもたくさんのテンレートがありますが、テンプレートの文章は当り障りのない文章となっており、相手の印象に残りにくい傾向があります。
特に優秀な人は、多方面からスカウトが来ているため、まずメールを読んで関心持って貰うには、相手の魅力を理解し、自社に来てほしいと感じているかをしっかりと伝える必要があります。
テンプレートの文章を元にして、よりオリジナリティー溢れる内容を盛り込みましょう。
・自社とマッチする部分を入れよう
価値観が合う・合わないというのは、どのような場面でも重要な問題です。
従業員を採用する際には企業が求める企業理念や価値観について、しっかりと理解している人を採用しなければ、思うような成果は出せません。
自社にはこのような価値観があり、その価値観がスカウトする相手とマッチすると感じる部分があったため、今回スカウトするに至ったというように、自社の価値観についても、スカウトした理由に触れておきましょう。
・入社後の利点について書こう
今は忙しい、機会があれば転職したいというように積極的に転職活動はするつもりはないが、いずれ転職をしたいと考える転職潜在層は、ありきたりのスカウトメールを送っても、閲覧して終わってしまう可能性もあります。
そのような転職潜在層にも読んでもらうためには、入社後の利点についても、触れましょう。
現在のスキルが活かせる、仕事とプライベートの両立がしやすいなど、メールを見た相手が思わず関心を寄せたくなるような、利点について書いておきましょう
ただし、あまりにも自社を良く見せるために、内容を誇張して書きすぎると、入社後にギャップを感じ早期退職となってしまい兼ねないので、あくまでも正確な情報を書くようにしましょう。
ダイレクトリクルーティングサービスを利用するのも一つの手
ダイレクトリクルーティングは工夫すれば自社で経験を活かし、活動していくことは可能です。
ですが、導入したばかりでノウハウが分からない、導入したが、なかなか思うような結果が出ない場合は、ダイレクトリクルーティングサービスを利用してみるのも手です。
慣れてきたり、ある程度経験を積んできたりしたら、自社で運用を行うようにしてみるのも良いでしょう。
まとめ
今回はダイレクトリクルーティングで落とし穴や弱点などを元に、ダイレクトリクルーティングを成功に繋げるポイントなどをご紹介してきました。
ダイレクトリクルーティングは企業が入社して欲しい人物に直接アプローチできる方法ですが、成功へ導くには弱点やデメリットについてしっかりと把握しておく必要があります。
ダイレクトリクルーティングを成功させるには上手なスカウト方法も大切ですが、魅力のある会社作りも欠かせません。
ダイレクトリクルーティングの運用で悩んでいる会社、これから導入しようと検討しようと考えている企業は、この記事を参考にしてみて下さい。