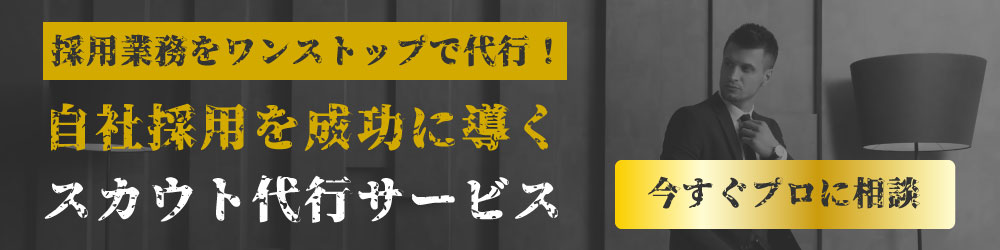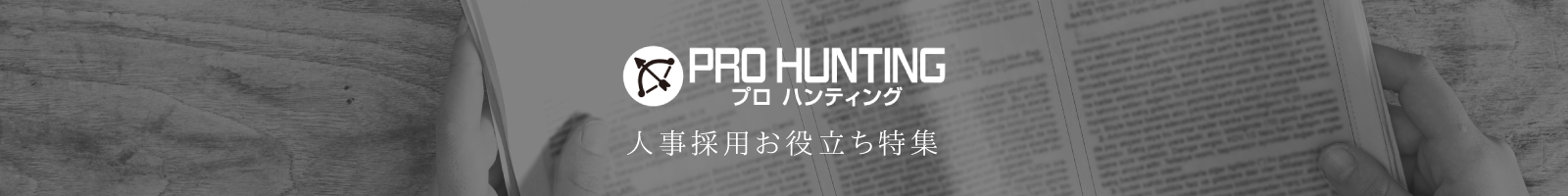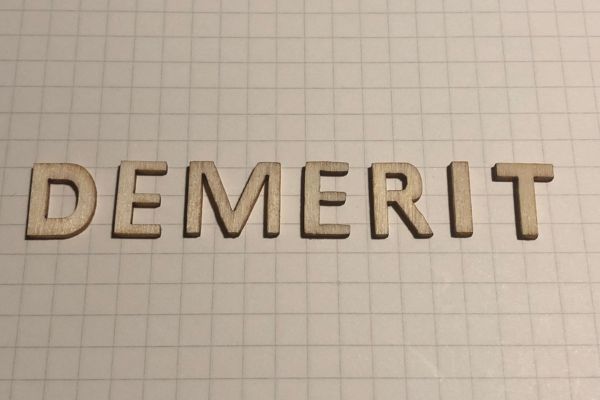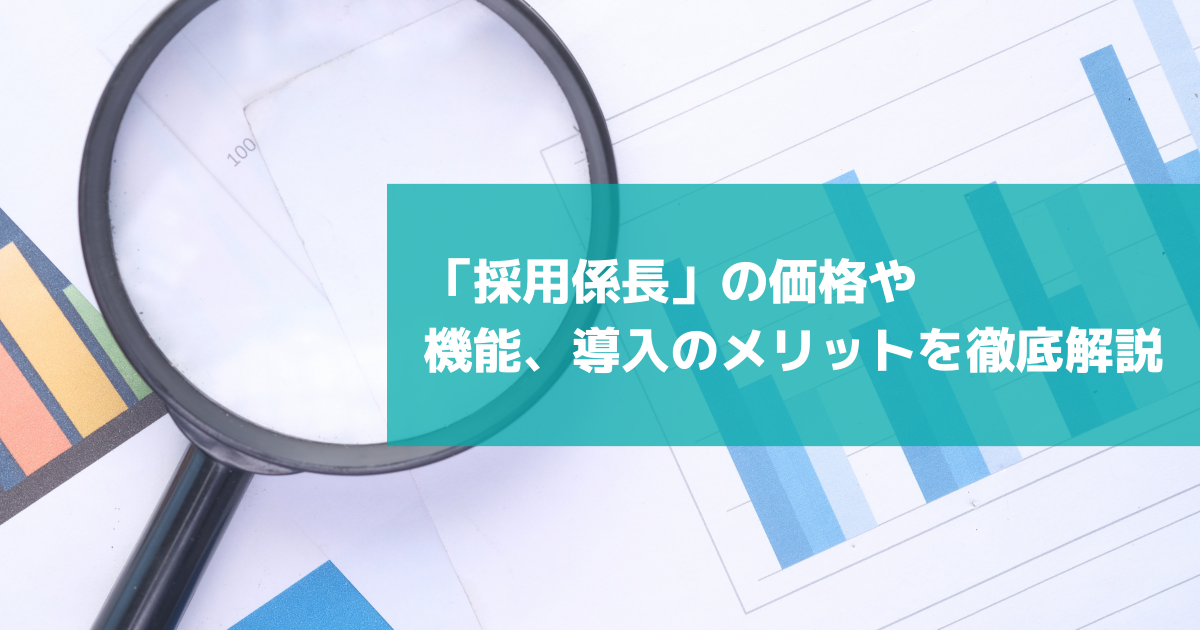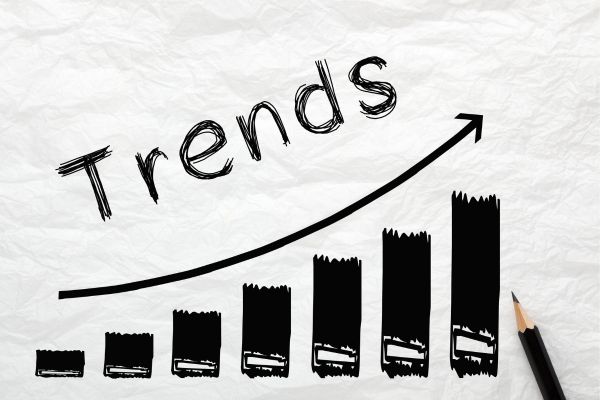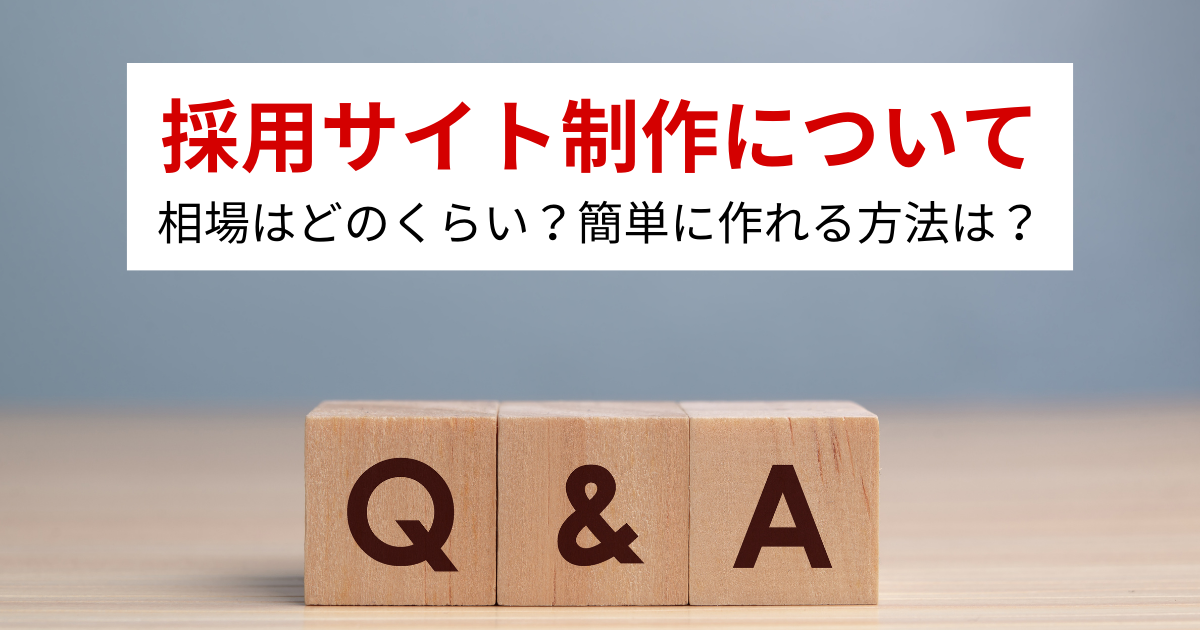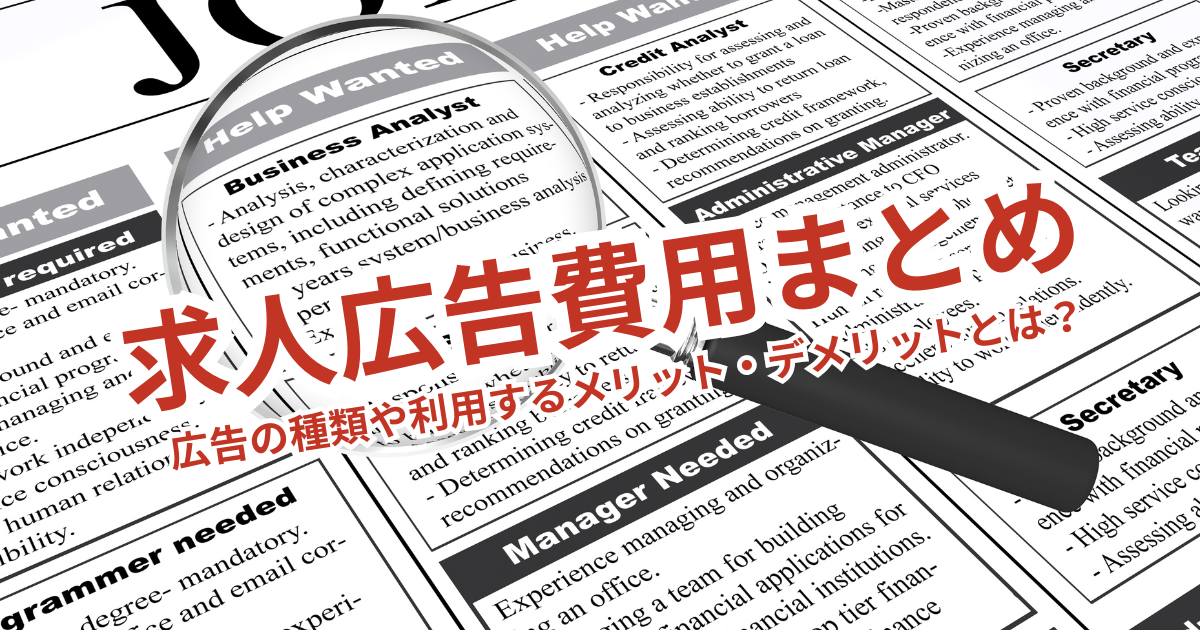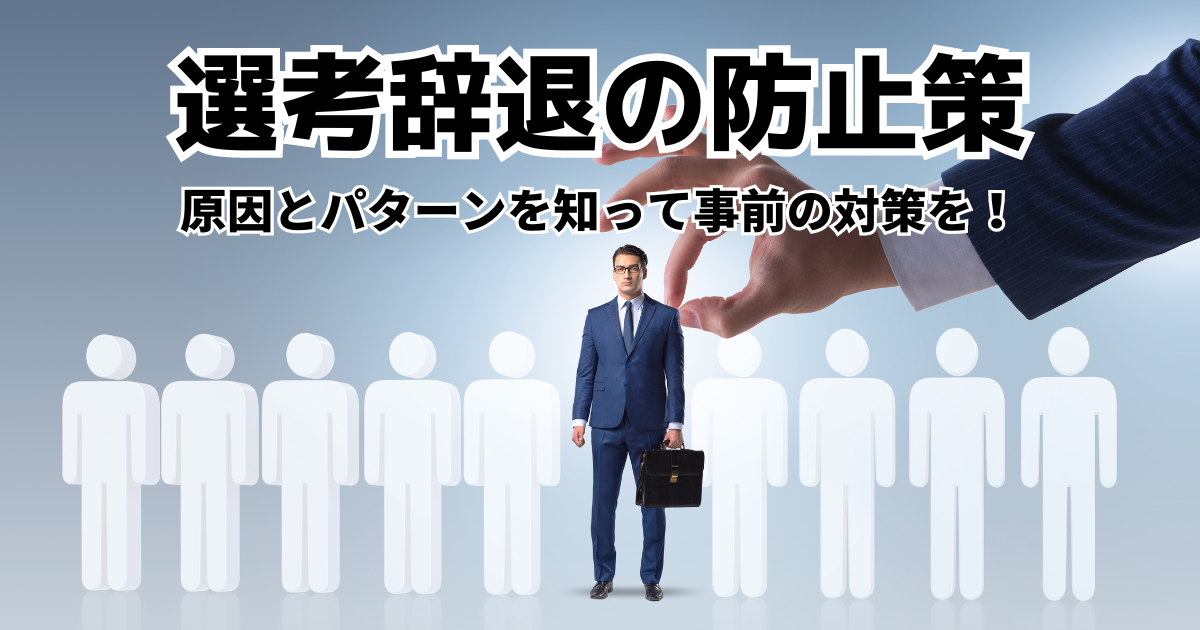採用活動の場で、このような人物を採用したいと、ターゲット像を明確にするために設計されるのが、“採用ペルソナ”です。
採用活動をしても、求める候補者が来ない、早期退職者が増えてきたなど、採用活動に悩む担当者は少なくありません。
採用活動を行う際、採用ペルソナを作り、どのような人物を求めているのか、具体化することで、候補者の集め方や採用方法などの戦略を練りやすくなるため、ミスマッチが出にくくなるというメリットがあります。
今回は、採用ペルソナを作り方、設計のコツやフォーマット例についてご紹介致します。
採用ペルソナとは

採用ペルソナとは、採用したい人物を具体的にイメージした人物像の事を指します。ペルソナと言う言葉は、もともと商品購入やサービス利用者などマーケティグの場で利用されており、顧客の典型的なタイプを具体化したものです。
内容としては、性別、年齢、居まい、前職や卒業校、趣味や所持している資格、性格、ライフスタイルなどが挙げられます。
少子高齢化で、採用競争が続く中、より具体的なモデルを作成することは、採用戦略を練るために効果的な方法と言われています。
採用ペルソナ作りのポイント

採用ペルソナ作る際のポイントについて、3つご紹介致します。
・採用担当部署と現場および経営陣の意見をすり合わせる
実際に候補者を集めたり、イベントや就職説明会などで求職者と顔を合わせたりするのは、採用担当者です。
ところが採用決定権があるのは経営者で、入社後に候補者が実際に働くのは現場です。そのため、採用担当者と現場、さらに経営陣と思い描く採用ペルソナがずれてしまっている事も少なくありません。
採用担当者は基本的なマナーや性格、現場サイドはコミュニケーション能力や技術力、経営陣は経営理念への理解度など、目指すターゲット像にズレが生じてしまうと、本来求める人物像からかけ離れたペルソナとなってしまいます。
採用担当者、現場および経営陣との意見をしっかりすり合わせて行きましょう。
・理想論ではなく現実的な対象を作る
ペルソナは、実際に職場で働くモデル像になります。ペルソナを作るときに気を付けなければいけないのが、理想像を描きやすい点です。
あれもこれも持っている人と言うように、理想的な人物像を追うのではなく、自社の市場価値(認知度の高さや企業規模)、採用市場全体の動きを調べ、現職員のこれまでの経歴及び成果など総合的に見て作成しなければ、会社が求める人物像とかけ離れたペルソナが出来上がってしまいます。
求める項目が多すぎると、候補者集めから難航してしまいますし、たとえ能力や技術力が理想に近くても、社風に合わないなど、別の項目でズレが生じてしまい兼ねません。
社内外を取り巻く環境を見つつ、現実的なペルソナを作成しましょう。
・複数のパターンを用意する
ペルソナは、一回の募集につき一人の人物像を描くのが理想的です。ただし、一つのペルソナだけで応募者を決定していると、内定者の傾向に偏りが生じてしまう可能性があります。
採用の目的に応じて、ペルソナを複数用意しておくと、採用者に多様性が生まれ、将来の事業内容や、採用目的ごとに複数のパターンを用意しておきましょう。
・社内で共有する
ペルソナを作成したら、社内で共有しておきましょう。今会社でどのような人物を求めているのか、一つの指標となるためです。
作成されたペルソナが、理想的過ぎていないか、経営者の声に偏り過ぎていないか、社内で共有し、微調整してきましょう。
・必要に応じてブラッシュアップする
ペルソナは、社会情勢や会社の状況、採用市場など、時代や状況に応じて調整していく必要があります。
採用市場は、経済全体の状況によって大きく変化します。特に売り手市場と呼ばれている近年は、候補者集めの段階で難航してしまう事も考えられます。
候補者が集まらない、ペルソナに近い母集団形成が出来ないなど、採用活動が難航する場合、ペルソナに何らかの問題があるのかもしれません。
必要に応じてブラッシュアップして行きましょう。
採用ペルソナの作業ステップ
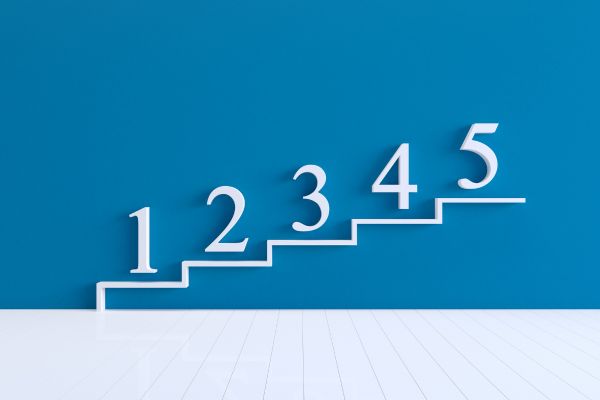
では、具体的なペルソナの作り方をご紹介していきます。
・社内外を環境分析する
採用ペルソナを作るには、手始めに社内外の環境を知ることから行います。社内外のさまざま要素を基に分析しています。
・3Ⅽ分析
自社を取り巻く環境を分析する方法に、3Ⅽ分析というのがあります。
3Ⅽとは、3つの要素( Customer=市場や顧客、Competitor=競合他社、Company=自社)の頭文字から取られており、もともとマーケティング分析で利用されていました。
すなわち、自社の認知度や会社規模などの市場価値、競合他社の状況、さらに社内環境などを総合的に見て、自社を取り巻く環境を分析しようという考えです。
・SWOT分析
分析方法として、もう一つ上げられるのがSWOT分析です。社内外の状況を4つの項目に分けたフレームワークです。
4つの項目はとは、Strength(強み)、weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)で、それぞれ頭文字を取ってSWOTと呼ばれています。
自社の強みや今後の課題、新規事業への機会、自社を脅かす競合や、法改定など自社ではどうにもできない外部環境などを、それぞれのフレームごとに分析してきます。
・採用目的の明確化
次に採用目的を明確にします。
例えば、会社の課題強化であれば、強化したいスキルを持つペルソナを作成しなければなりませんし、新卒採用であれば、今後の“のびしろ”に期待したペルソナを作るようにします。
今回求人募集する目的が何なのかを明らかにし、関係者が同じゴールを目指すため、採用目的を関係者の間で明確化します。
・現場サイドとのヒアリング
次に、現場サイドとのヒアリングです。採用後に実際に業務をするのは現場です。現場がどのような人材を求めているのか確認する事は、ミスマッチを防止するためにも重要です。
たとえば、職場や職種により、チームワークを必要とする、ある程度個々の裁量が求められるなど、違いがあるでしょう。
採用者が今後働く現場でどのような項目にポイントを置くのか、ヒアリングをしておきましょう。
・必要条件の洗い出し
次に、実際に職場で活躍している人物をモデルとして、項目ごとに基準を設けます。
項目は、“定量”、“定性”の2つに大別されます。
- 定量要件…年齢、学歴、言語、家族構成、居住地、職歴、勤務条件、健康状態、スキルなど、その職場で働くための必須条件です。
- 定性要件…価値観、志望動機、ビジネスマナー、ストレス耐性、適応性、キャリア志向など、定量では図りにくいが、業務で必要とされる条件です。
各職場で働く優秀な人材を、定量・定性項目ごとに洗い出し、今回の採用活動で必要とする人材要件を選んでいきます。
その際、項目が多くなりすぎたり、条件が高度になりすぎたりしないよう、必須要件(MUST)と、あると望ましい要件(WANT)に分けて優先順位を定めて行きます。
・ペルソナのたたき台の作成
必要条件の洗い出しや現場とのヒアリングを基に、実際にペルソナのモデルを作っていきましょう。
その際、ハイレベルな社員に共通する項目を入れる、必ず入れたい要件や望ましい条件などのバランスを考え、さらに経営陣、現場サイド、採用担当者などの意見をすり合わせて行きます。
また、ペルソナはあくまでの架空の人物ですので、複数のパターンを考えておくのも一つの手でしょう。
・採用市場の状況と隔たりが無いか確認する。
仮のペルソナを作成したら、競合他社と採用市場の中で隔たりが無いか、確認しましょう。理想を求めるあまり、ハイスペックになりすぎたり、条件が偏りすぎたりすると、その後の採用活動が困難になってしまいます。
例えば、求人数が多く、他者との競争が激しい事が予想される場合、やむをえず、採用条件を下げる事も有効な採用戦略になり得ます。
自社が求める理想の人材を追うだけではなく、自社の認知度や市場全体の求人数、競合他社の条件などを総合的に判断し、ペルソナを微調整していきましょう。
・社内の合意を得る
社内外の状況を基に、ペルソナを作成したら、関係各部署の合意を得ましょう。その際、現場からやり直しや、上層部からもっと高いレベルを求められるかもしれません。
その場合は、具体的にどの条件の修正が必要なのかを確認するとともに、社内外の採用市場との状況や競合他社の条件などを基に、このペルソナになった要因を説明して行きましょう。
さらに、社内全体に合意を得て、共有します。特に面接に携わる部署関係者には、内容を共有しておきます。
・活動結果を見て見直す
作成したペルソナを実際の採用の場で活用してみましょう。活動の結果を見て、候補者が集まらない、ペルソナと掛け離れた人物が応募してくる、選考辞退や内定辞退が多い場合、ペルソナに何らかの問題があることが考えられます。
必要に応じて、定期的に見直しを行っていきましょう。
採用ペルソナのメリット
採用ペルソナには、次のようなメリットがあります。
| ・雇用条件の作成に繋がる ・採用目的が明確化しやすい ・早期退職者防止の分析につながる |
ペルソナで候補者が具体化するため、雇用条件が作成しやすくなります。さらに採用の目的が明確化するため、社内で共有やすくなります。
合わせて、内定辞退者や早期離職者との傾向を合わせれば、早期退職者を防止にもつながるでしょう。
採用ペルソナのフォーマット例

それでは、実際に採用ペルソナの例をご紹介致します。
・新卒採用の場合
氏 名:〇〇 〇美
年 齢:22歳
性 別:女性
最終学歴:〇〇大学 〇〇学部卒
居住地 :〇〇都
家族構成:両親と高校生の弟1人と4人暮らし
能 力:TOEIC600点 PCスキル(Word、Excel、PowerPoint)
休日の過ごし方:ヨガ、ダンス
価値観 :小さな頃からダンスを習っており、体を動かすことが好き、チームで一つの事を成し遂げることに達成感を感じる
志望動機:人事部希望:人とコミュニケーションを取る事が好きで、誰かの約に立てる事が好きなため応募した
・中途採用の場合
氏 名:〇〇 〇男
年 齢:35歳
性 別:男性
最終学歴:〇〇大学 〇〇学部卒
居住地 :〇〇県
前 職:WEBエンジニア
前職年収:500万円
家族構成:妻と2人暮らし
能 力:モバイル開発、WEBエンジニア
休日の過ごし方:映画鑑賞、オンラインゲーム
価値観 :スキルアップや技術力向上に強い関心がある
志望動機:結婚し今年中に家族が増える予定。今後に備えスキルアップ考え応募した
まとめ
今回は、採用ペルソナの作り方についてご紹介してきました
採用活動において、ペルソナを作成する事は、採用ターゲットが具体化するため、有効な方法です。ペルソナを作成するときは、単に優秀な社員の項目を分析するだけではなく、自社の状況と共に、採用市場全体から見た立ち位置、現場サイドとの調整を行い、設計を行っていく必要があります。
自社にマッチする採用ペルソナを作成することで、明確な採用目的や雇用条件の作成が出来るため、早期退職の防止にもつながります。
採用ペルソナの作成に悩む企業は、この記事を読んで参考にしてみて下さい。