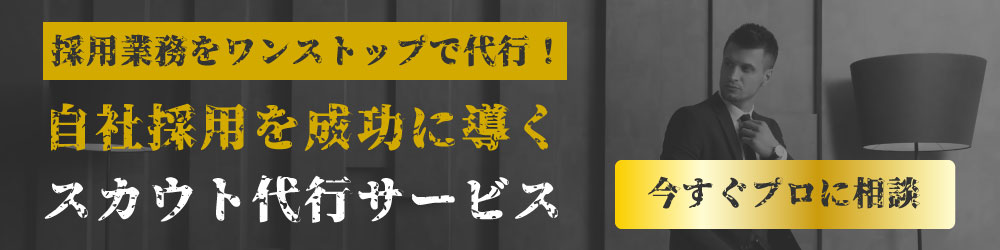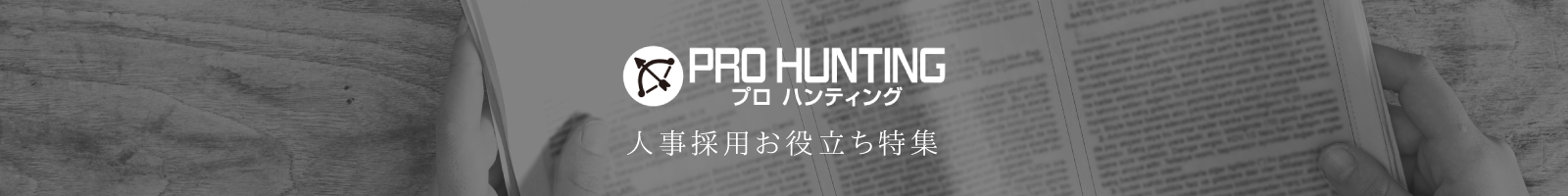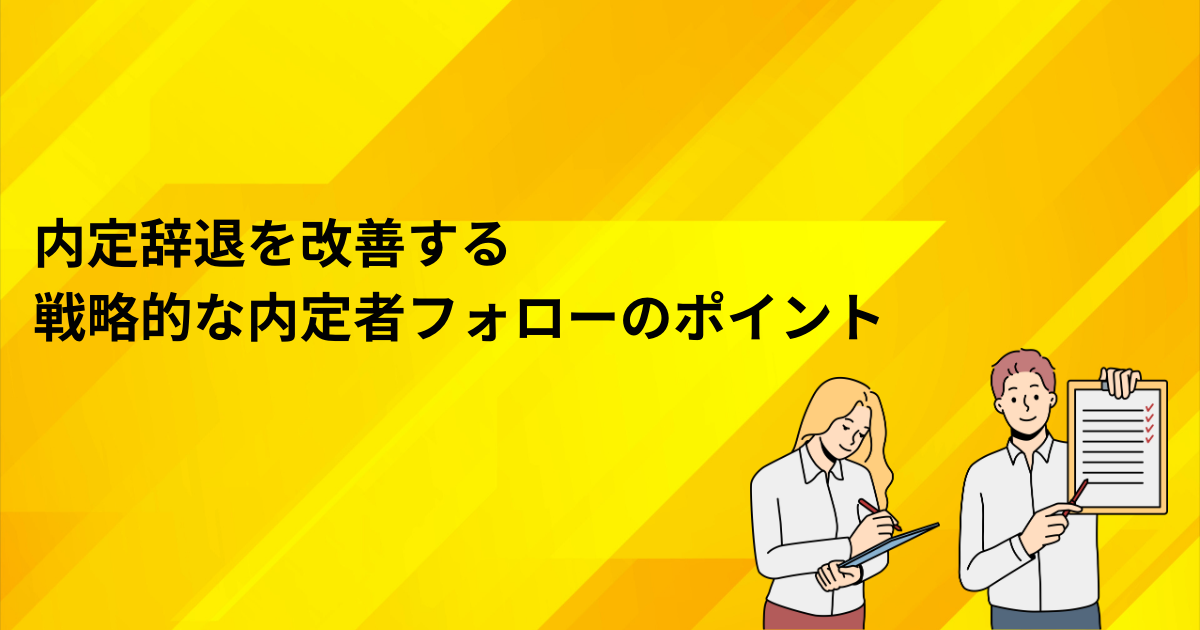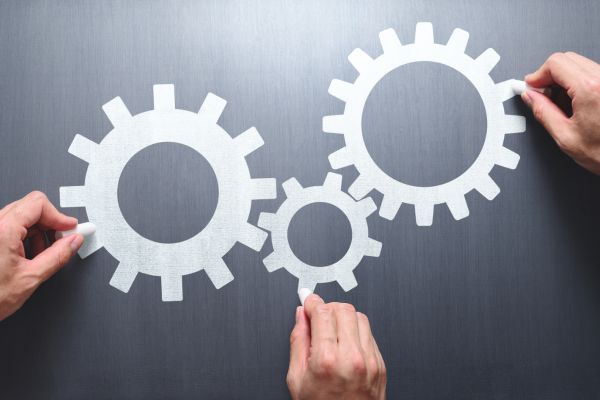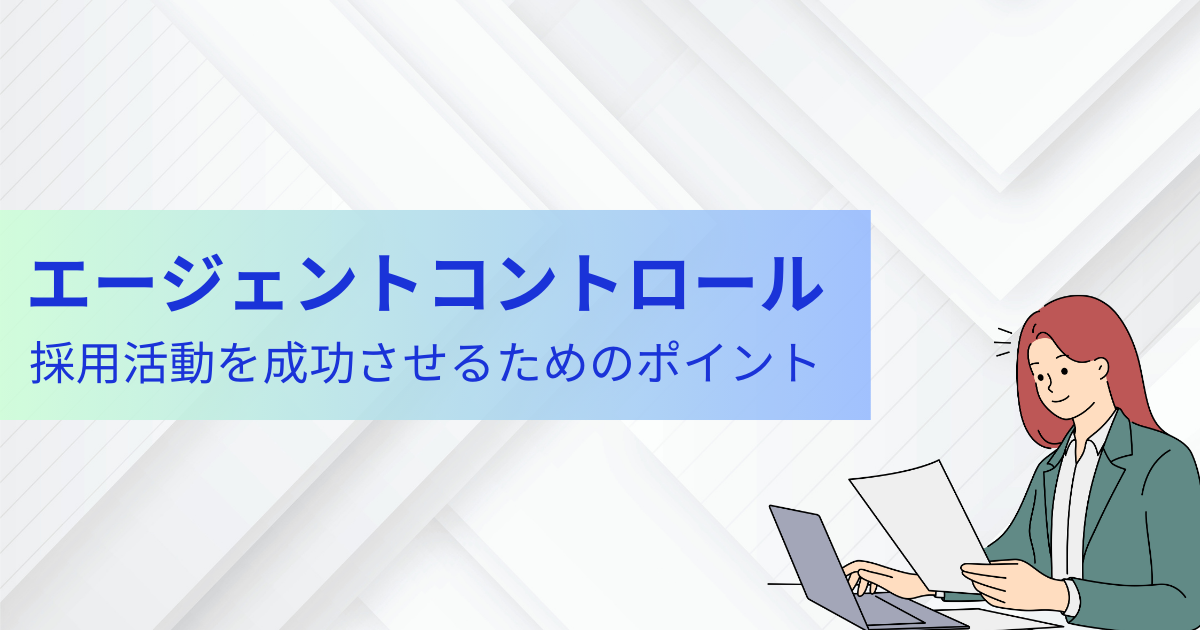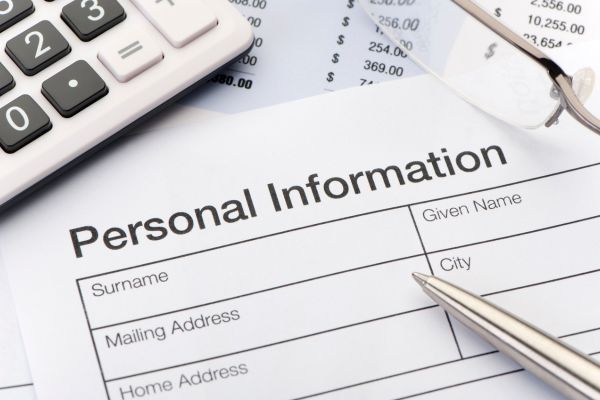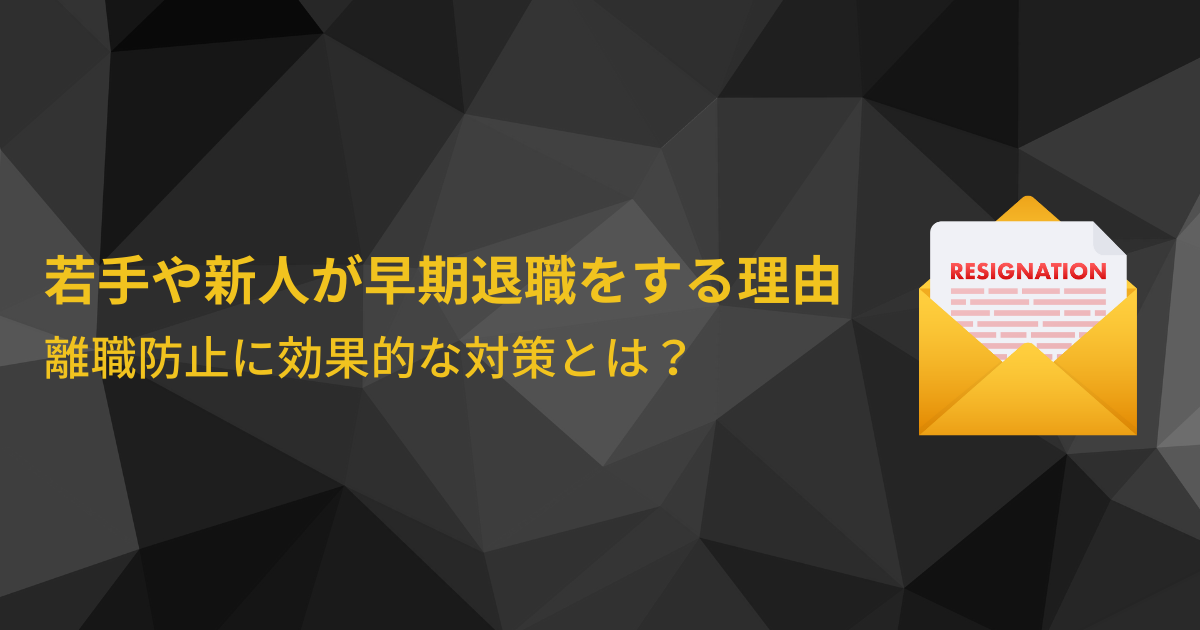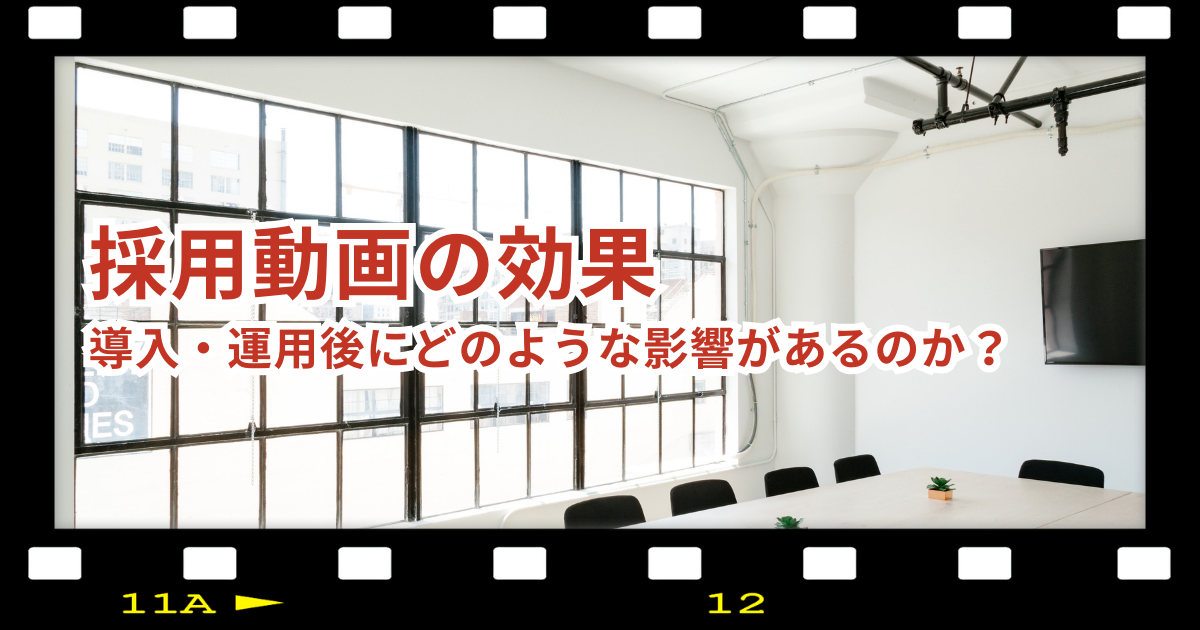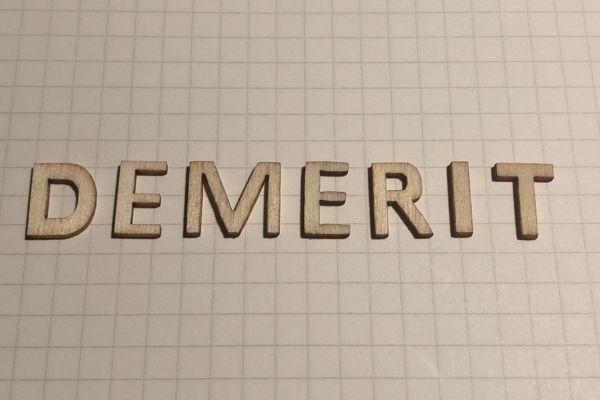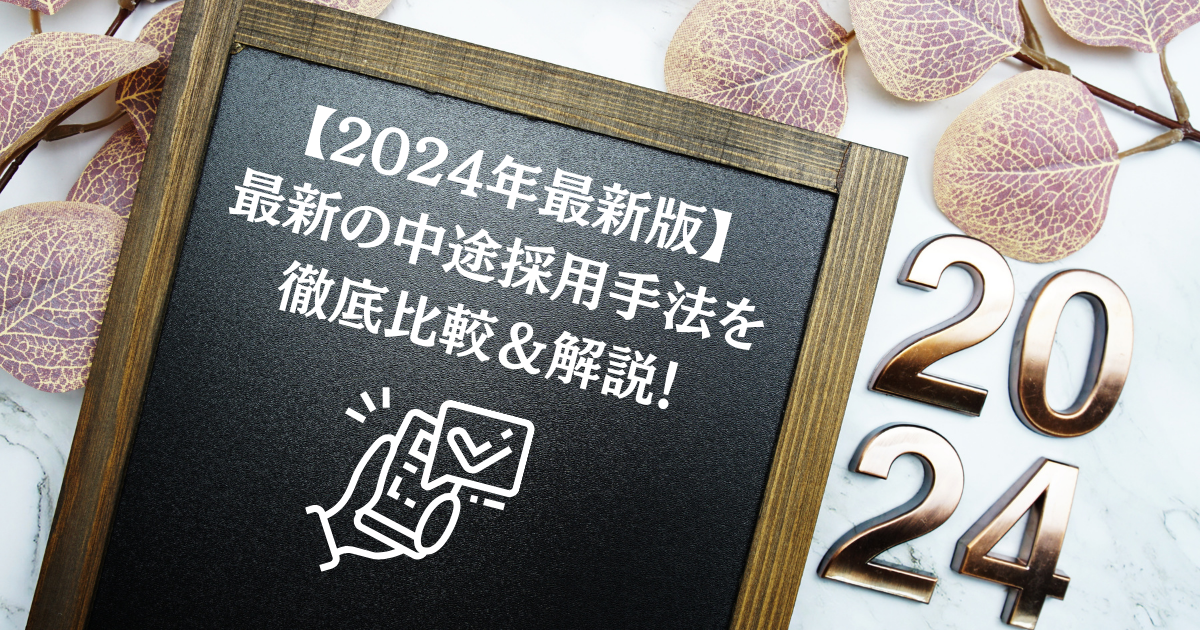就活生が職業体験を行うインターンシップは、採用活動にとって欠かせない工程の一つです。
2025年卒業生より、インターンシップの定義が改定され、インターンシップで得た情報を採用活動で利用する事が可能になりました。
今回は、これまでのインターンシップの内容と、2025年卒より改定される採用直結型インターシップについて、解説致します。
25年卒解禁の採用直結型インターンとは

2023年に経団連と大学との対話で発足した産学協議会(採用と大学教育の未来に関する産学協議会)にて、従来のインターンシップを以下の4タイプへと分けました。
| インターシップと称さない | インターシップと称して実地する |
| ・タイプ1:オープンカンパニー ・タイプ2:キャリア教育 | ・タイプ3:汎用的能力、専門活用型インターシップ ・タイプ4:高度専門型インターシップ(試行) |
・タイプ1:オープンカンパニー
主に会社㏚や業界の案内や情報案内を行います。個社や業界に関する情報共有を目的としており、参加学生の年次は不問です。参加への敷居は低く、だいたい1日程度で行われることが多いです。
職業体験は伴わず、時間帯やオンラインの活用など、学業の妨げとならないよう配慮されています。
・タイプ2:キャリア教育
働くことの理解を得るための“教育”を目的として行われます。内容としては、学校側が主導する授業や産学協働プログラム、企業がCSR活動として用意したプログラムがあります。
タイプ1のオープンカンパニータイプと同様、参加年次は問わず、どの学年でも参加可能です。所要日数は、授業やプログラムによって異なります。
・タイプ3:汎用的能力、専門活用型インターシップ
下記の必須要件と情報開示要件を満たすことで、“インターンシップ”と称する事が可能なタイプです。
学生が実際に“職業を体験”することで、学生が自分の能力を知り、企業も学生の適性を判断する目的で行われます。対象も大学3、4年、修士1年、2年、博士課程学生と決まりがあります。
ここでのポイントは、職業経験が必須となっている点でしょう。職場で社員の指導の下、業務の一部を行ったり、企業のみ、もしくは大学と企業の協力で構成された、専門性の高いプログラムを行ったりします。
インターンシップ必須要件として、次の4点が求められます。
- 職業体験要件:実施期間の半分超える日数を職場で職業体験する
- 指導要件:職場社員が直接学生に指導、及び学生にフィードバックする
- 実施期間要件:汎用的能力活用型 5日以上、専門活用型2週間以上
- 学校が長期休暇の期間(夏休み、冬休み、春休み、入試休み等)
- 情報開示要件;プログラム主旨や体験内容、実施時期など
取得した学生情報は、就活ルールに法り、卒業、修了年次の前年の3月以降は広報活動に、卒業、修了年次6月以降は選考活動に活用が可能です。
・タイプ4(試行中):高度専門型インターンシップ
学生の実践力向上と学生の評価材料の取得を目的としています。現在試行中でありますが、高度な専門性を意識したインターンシップや、ジョブ型研究インターンシップなどを想定しています。
職業体験はタイプ3と同様、必須要件となっており、インターンシップで得られた就活生の情報は、採用活動開始に限り使用しても良い事になっています。
禁止要請だった採用直結型インターンシップが解禁となった背景

就職活動のルールである就職協定は、1953年に定められました。しかし効果は薄く、水面下で行われる、就職活動の早期化は無くならず、改定や廃止、新たなルールを繰り返し、2013年に経団連が「採用選考に関する指針」を制定します。
ですが、2018年にルールが形骸化している点や、通年採用を導入する企業が増えてきたことから、経団連は、就活ルールを廃止しました。その後は混乱を避けるため、政府がそれまでの就活ルールを引き継ぎ、現状維持と言う形に落ち着いているのが現状です。
当時からインターンシップは、企業が就活生に実際に職業体験し、事業内容や企業風土を理解して貰うと共に、学生の適性を判断するために行われる有益な活動であるとされていました。
しかし、実際には、就職説明会に近かったり、採用活動に近い事が行われたりする事があり、本来の目的である職業体験とは異なる“採用につながるインターンシップ”になりつつあり、こうした採用に直結するようなインターンシップについて禁止要請が出される事となりました。
しかし、あくまでも禁止“要請”であり、法的な効力はなかったこと、売り手市場により、採用競争の激化が続いていたこと、ベンチャー企業や新規事業などでは、こうしたルールが守られて事も多かったことから、2025年卒の以降、ガイドラインを設けた上で認可するという形になったのです。
「タイプ3 汎用的能力、専門活用型インターシップ」に参加した学生のリアルな声は

タイプ3の汎用的能力・専門型インターンシップでは、どんな事が行われているのでしょうか。就職みらい研究所で公表された、2025年卒インターンシップ・就職活動準備に関する調査を基に、実際に参加した学生の声を集めてみました。
理系大学生
- ソースコードをひたすら改良していくプログラミングを行った
- 実際に発案や設計、開発を行った
文系大学生
- 学校事務での業務で、生徒対応や文化祭の準備、データ入力や掲示板作成を行った
- 商品の販売を行い、フィードバックを受け、修了式ではまとめを発表した
- 銀行のRM(リレーションシップマネージメント)として、大企業へ提案を行った
理系大学院生
- 3週間ほとんど実務経験をした
- オリエンネーションや工場見学、就業体験、成果発表を行った
- メンター指導の下、アプリ開発のタスクの一つの実装やレビューなどの実務を行った
- 指定部署にて2週間、開発設計業務などを行った
- 2つの部署で、1年目の実務業務に触れた
上記、実際に参加して声を見てみますと、部署へ配属され、社員から指導のもと、実務経験をしている事が分かりました。
採用直結型インターンシップの認知度

従来のインターンシップから、2025年卒者より改定となるインターンシップですが、就活生の、認知度については以下のようになっています。
採用直結型インターンシップの認知度
就職みらい研究所の2025年卒インターンシップ・就職活動準備に関する調査によりますと、インターンシップがキャリア形成支援の取り組みとして、4種類のパータンに分かれて事を、知っている43.7%、知らない56.3%という結果になりました。
「タイプ3 汎用的能力・専門型インターンシップ」の認知度
改定により、インターンシップと称する事が可能なタイプ3の認知度は、44.3%にとどまっています。
しかしタイプ3の概要を知らなかった学生も含め、インターンシップについて説明した大学生全体のうち、7割以上の学生が参加を希望しており、参加意欲の高さが伺えました。
ところが、実際に5日以上のインターンシップなどのキャリア形成支援プログラム参加率は18.2%にとどまっており、まずは学生への認知度を上げる事が課題の一つと言えるでしょう。
採用直結型インターンシップのメリット・デメリット
採用直結型のインターンシップのメリット・デメリットを見て行きましょう。
メリット
就活生の企業理解度を深める事が出来る
メリットとして第一に挙げられるのは、実際に職場で業務を行う事で、社風や企業理念を理解する事が出来る点です。
現場で実際の業務の一部を行うことで、仕事へ心構えが生まれ、アルバイトとの違い、責任感の重さを知るようになります。さらに社員から直接業務のフィードバックを行う事で、社内環境が分かりやすくなります。
企業側も就活生の能力を判断出来る
一定期間、実際に就活生が業務を行う様子を見る事で、就活生の能力を判断する事が出来ます。
進行の流れや不明点があった場合のコミュニケーション能力、指示への理解度などを判断でき、タイプ3のインターンによるプログラム参加者であれば、その内容を、採用へ繋げる事が可能です。その結果、採用のミスマッチが少なくなります。
採用の効率化へとつながる
上記①と②の理由により、採用活動前に、就活生とのマッチ度が分かるため、就活生も企業側も採用活動の効率化が図れることになります。
タイプ3、4の参加者情報は、そのまま採用活動へ利用可能になりますので、採用活動や選考期間を短くすることが可能になります。
デメリット
工数が掛かる
タイプ3の汎用的能力・専門型インターンシップは、実際に職務体験を伴う事が必須要件で、汎用的能力活用型では5日以上、専門活用型2週間以上の期間は、学生を受け入れなければなりません。
その間、社員が実際の業務を教え、フィードバックも必要です。期間も学生の長期連休に合わせて行わなければならず、インターンシップ担当に就いた社員にとっては、大きな負担となるでしょう。
また、どこの部署で、どのようなプログラムで行うのか、担当者の数など、十分に検討しなければならず、受け入れには工数が掛かるため、入念な準備が必要となります。
インターンシップと称するには条件がすべて揃っている必要がある
インターンシップと称するには、上記のタイプ3、タイプ4の条件を満たす必要があります。今回の改定では、職業体験要件、 指導要件、 実施期間要件、学校が長期休暇の期間であること、情報開示要件など、各種要件を満たしていなければなりません。
採用希望者から辞退されるリスクがある
職業体験といっても、5日間~2週間ほどで、すべての実務を教えていく事はムリがあるでしょう。
実態に沿った職業体験をさせようとするあまり、難易度の高い体験をさせてしまったり、反対に簡単すぎる体験だったりすると、志望度が下がってしまう可能性があるため、プログラム内容を吟味しなければなりません。
また優秀な学生で、企業側が採用希望を出しても、学生がプログラム内容で得られるものが無かった、内容が自分には合わないと判断すれば、辞退されてしまう可能性もあります。
まとめ
今回、2025年卒業生より改定された、採用直結型インターンシップの内容を中心に、インターンシップについて、ご紹介してきました。
これまで、採用と直結するインターンについて、禁止要請が出されていました。ですが、法的拘束力がなくルールが形骸化されていたこと、通年採用が増えてきたことから、明確なルールを出し、採用直結型インターンシップを解禁することとなりました。今後さらにインターンシップが、採用活動において、重要な意味を持つことが予想されます。
採用直結型インターンシップに興味のある企業や、インターンシップについて悩む企業は、この記事を読んで参考にしてみて下さい。